目次
近くの公園に補助付きの自転車を30分ー100円で乗れるスペースがあります。子どもが幼い頃、よく連れて行きました。1周、100メートルに満たない小さなコースです。
土日になると、子供たちでひしめきあいます。補助付きですので、乗っているのは、3歳〜5歳くらいの幼稚園生です。私の息子は、慎重すぎるくらい慎重なタイプで、決してスピードを出そうとしません。ノロノロ、ノロノロ。同じスピードで走り続けます。
その横を、息子より小さな女の子が、ものすごいスピードで、チリンチリンと音を鳴らしながら追い抜いていきます。歌を歌う男の子が抜き去り、次にはまるで怒っているかのような大きな声を出す子が、さらにスピードを上げて抜いています。
我が子は、それに対して競争心がわくことがないようで、同じスピードで亀のよう走っています。父親からすると「もっと男らしく速く走れないものか」と、こっちの気持ちが急いてしまいます。

ただ、そんな様子を見てつくづく思ったのは、幼い子供たちが実に「個性」にあふれ、「人それぞれ」だということです。もし、全員が同じスピードで、同じ様に、同じ顔して走っていたら、それはつまらない光景ですね。
みんなそれぞれ。だからこそ、その光景はイキイキとしていました。
そう考えると「個性」があるから、世界は彩り豊かになり、やはり人はそれぞれがもつ「個性」を、大切にしなければと感じます。
2003年に出版され400万部を超える大ベストラーとなった本といえば『バカの壁』(新潮社)です。著者は、医学博士で解剖学者の養老孟司先生。現在は、東京大学名誉教授です。

クリックするとAmazonへ!
この本で養老先生が「個性」について、ふれている所があります。
本来意識というのは共通性を徹底的に追求するものなのです。その共通性を徹底的に確保するために、言語の論理と文化、伝統がある。人間の脳の特に意識的な部分というのは、個人間の差異を無視して、同じようにしよう、同じようにしようとする性質を持っている。
『バカの壁』(養老孟司 新潮社)
人の意識が「同じように、同じように」と「共通性」を追求するといいます。だとすると、人間の「個性」はなくなり、「平均的」「没個性的」になってしまいます。
では、養老先生は人間の「個性」をどこに見い出すのでしょう。
個性は「身体そのもの」である、と養老先生は主張します。サッカーの中田英寿選手や野球のイチロー選手を例にあげています。日本人は個性が弱いとよくいわれますが、「身体」を「個性」とするならば、「個性」は誰にでもあるものです。
脳 / 意識=共通性
身体=独自性→個性
脳や意識が「同じようにしよう」とする性質をもつため、私たちは、他人と同じ考えをもとうとします。出る杭は打たれる。集団の中で大禍なく過ごすには「みんなと違っている」より「みんなと同じ」の方が、安心できます。違っていると、それを材料にされ仲間外れにされたり攻撃されるかもしれません。
「身体」は、そうは簡単には、他人と同じにはなりません。顔や姿かたちは、人それぞれで、独自のものです。もちろん、似ていることはありますが、100%同じということは絶対になく、身体は誰もが「個性的」です。

養老先生は、「脳/意識」と「身体」を対立させています。「個性を伸ばそう」という考え方は、「脳/意識」が作りだしています。でも、「脳/意識」の性質は「共通性」を追求するのだから、矛盾するわけです。
「建前」と「本音」がすけて見えてきます。
「個性を伸ばそう」は建前であって、学校や職場で、他人と違う行動をとる個性的な人は、正直いえば困るのが本音でしょうか。
「みんなと同じ」が求められているのに、個性を伸ばしたら、他人との違いが目立ち、学校や会社という集団のなかでは、リスクにさらされます。イジメにあうかもしれません。
学校でも会社でも、本当に「個性を伸ばす」教育をするなら、相当な覚悟が求められるのです。
国際エコノミストとして著名だった長谷川慶太郎氏の著書に『異端のすすめ』(PHP研究所)があります。
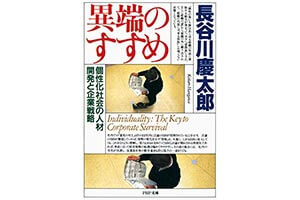
クリックするとAmazonへ!
タイトルから想像がつきますように、日本企業は、異端とは反対の「みんなと同じ」をよしとする「個性の弱い人材」を育成している、と批判します。こんな一文があります。
「個性の強い人物」は、はっきり言って経営者を含めた上役の意見にすぐさま同調できない人物である。(中略)
『異端のすすめ』(長谷川慶太郎 PHP文庫)
といって「個性ある人物」は、より広い視野に立つ、より緻密な論理を持った意見には屈しても、単なる思いつき、あるいはそれに類する浅薄な発想、不十分な論理しか持たない意見には容易に屈しない。
上役あるいは経営者にとって「個性ある人物」は決して簡単に使いこなせる人物ではない。それだけまた使いにくい側面があるが一方一旦、納得すれば、こうした「個性ある人物」ほど信頼できる存在もない。

長谷川氏の一文を読んで、アップル創業者スティーブ・ジョブズが頭に浮かびます。ジョブズは「個性の強い人物」です。特に若い頃は、非常に我が強く、クセのある人間でした。容赦なく人をこき下ろし、それが原因で社員が辞めていきました。そうした難のある人間性も災いして、一度、アップルを追い出されていますね。
ただ、ジョブズがいなくなったアップルは迷走し、業績が悪化します。そこでジョブズが復帰して、「iPod」「iTunes」「iPhone」など、次から次にメガヒット商品を生み出していくのです。
「上役あるいは経営者にとって「個性ある人物」は決して簡単に使いこなせる人物ではない。」
長谷川氏の発言は確かにその通りで、実際に、ジョブズのような「個性の強い人物」が部下にいるとしたら、マネジメントするのは大変で、胃が痛くなるでしょう。

「個性の強い人物」が多いと、組織の「和」が乱れかねません。「クセの強い」人材ばかりでは、チームがまとまらず組織力は落ちていきます。しかし「みんなと同じ」考え方しかできない人間ばかりでも、新たなイノベーションが生まれず、組織の未来は危うくなるでしょう。
「個性を伸ばそう」はいいのですが、組織という枠組みの中で「個性」を考えると、その程度に応じて、メリット・デメリットがあるものです。
ジョブズはこの世界に革命を起こした歴史に残る偉人であり、ビジネスリーダーの理想です。かと言って、社員全員がジョブズのような「個性の強い人物」だったら会社は成り立たないのです。
「個性を伸ばそう」。そう言われるのは、日本人の「個性の弱さ」が課題になっているからですね。人と違うことを恐れてしまうのは、学校の生徒だけでなく、社会人にも見られる傾向です。
養老先生の言う、脳の生み出す意識が「共通性」を求めているとしたら、「没個性化」は、当然の帰結に思えます。日本では、学校で決められた制服があり、全員が同じ格好をしているのは「没個性化」の典型です。
でも、欧米の「個人主義」とは異なる「個の意識」が日本人にはあります。ですので、「個性の強い人物」=「個性的な人」とは、ならないのが私たちの「個性観」です。
心理療法家の河合隼雄先生は、『日本人とアイデンティティ』(講談社)で、こう書いています。

クリックするとAmazonへ!
欧米人が「個」として確立された自我を持つのに対して、日本人の自我──それは西洋流に言えば「自我」とも呼べないだろう──は、常に自他との相互的関連のなかに存在し、「個」として確立されたものではない、ということであった。
西洋人からは、この点に関して日本人の無責任性とか、他人志向性などと言って非難されることもある。ある西洋のビジネスマンは筆者に対して、日本人と交渉するときは、誰が本当の責任をもっているのかわからないので困ると言ったことがある。
ある人と交渉すると、「上司と相談して」と言う。そこで、その上司と直接交渉すると、「部下と相談して」と言う。いったいどうなっているのか、というのである。
河合先生の論を考えに入れると、そもそも「自我」の特性が異なるため、日本人の「個性」は、西洋流とは違うことがわかります。私たちが「個性を伸ばそう」と言葉にする時、イメージしている「個性」は、西洋流の「個性」であり、つまり「自我」の「強さ」を前提にしています。

西洋流の「個性」は、長谷川慶太郎氏のいう「個性ある人物」のことです。スティーブ・ジョブズのような自我が確立された「我の強さ」を前提にした「個性」です。例えば、小学校のクラスで、性格が明るく積極的に発言し、クラスのみんなを自然と引っ張る目立つ生徒を「個性がある」と考えます。
西洋流の「我の強い個性」を「個性」として求めるなら、日本人は「個性を伸ばす」必要があります。
でも、日本人の「個性」のとら方は、違うのです。
クラスで、いつも大人しくしている言葉数の少ない生徒は、個性的ではないのでしょうか。そうではないですね。日本人の「個性」のとらえ方は、そうした大人しい子にも「個性」を認めようとするところがポイントです。
日本は、たくさんの神様を共存させる多神教の文化をもっています。「八百万神(やおよろずのかみ)」が息づく国です。金子みすゞさんの詩「わたしと小鳥とすずと」にある「みんな違ってみんないい」のフレーズを多くの人が好意的に受け入れます。
個性が強くても弱くても、どちらにもメリット・デメリットがあり、個性の多面的なとらえ方を自然とするのが、日本人の「個性観」です。
| 個性(強い) | 個性(弱い) | |
| メリット | ・自己主張ができる ・違うことを恐れない ・孤独に強い | ・和を重んじる ・謙虚になれる ・協調性がある |
| デメリット | ・人と対立しやすい ・人の和を乱す ・自己中心的になる | ・平均思考 ・ノーを言えない ・自分の意見が少ない |
「知の巨人」梅棹忠夫は、日本人の「劣等感」を指摘しました。「ほんとうの文化は、どこかほかのところでつくられているものであって、自分のところのは、なんとなくおとっているという意識」(『文明の生態史観』中央公論新社)は、「西洋の方が上である」と考えがちな漠然とした劣等感を示しています。
西洋流の確立された強い自我から生まれる「個性」を前提とし、「なんとなく劣っている」という意識が抜けないために、学校にしても会社にしても、人を育てようとする時に「個性を伸ばそう」と、自虐的に連呼したくなるのです。
私たちは今も、戦後の高度成長期のような「西洋に追いつけ、追い越せ」のスローガンを、無意識のうちに実行しているかのようです。
私たち日本人は、世界の中で十分に「個性的」でありユニークな存在です。西洋とは異なる「心の特性」をもち、「和」を重じ様々な文化が花開き、経済も先進国で上位に入っています。
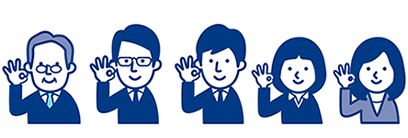
矛盾するようですが、「我の弱い個性」を持つからこそ、「個性的」なのが日本人なのです。
「個性を伸ばす」のではなく、「すでに、もっている個性を互いに認め合う」視点を養うことが「個性教育」のスタートラインであり、重要なことです。
歌を歌いながら速く走る子も「個性的」なら、ノロノロ亀みたいに走る子も「個性的」。
みんな違ってみんないい。人それぞれの個性を認めていきましょう。
(文 松山淳)



