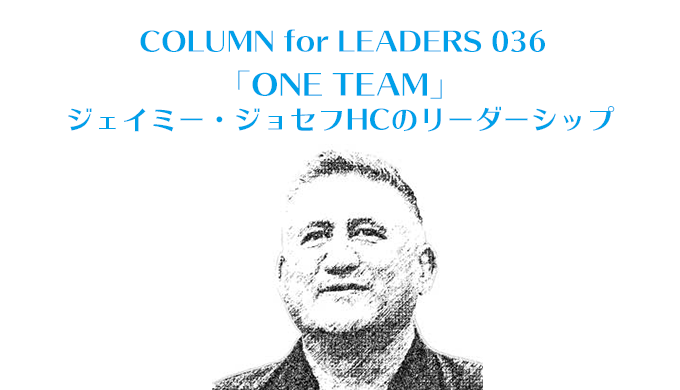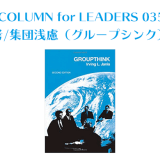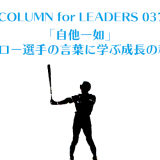「ONE TEAM」。ラグビー日本代表のチーム・スローガンである。2016年10月、ジェイミー・ジョセフHC(ヘッドコーチ)が記者会見で発表した。ラグビー日本代表はスローガン通り、チーム一丸「ONE TEAM」となって、2019年ラグビー・ワールド・カップ(日本開催)で初のベスト8進出を果たした。ジェイミーHCはどのようなチームづくりをしてきたのか。ジェイミー・ジョセフHCのリーダーシップに迫ってみたい。
目次
- 1 ジェイミー・ジョゼフとは?
- 2 指導者として「ハイランダーズ」を優勝に導く
- 3 Change(変えるべきは変える)
- 4 エディー流からの脱却
- 5 リーダーシップとは創造的破壊を行うこと。
- 6 戦略・戦術の変更〜キック&アンストラクチャー〜
- 7 Self-initiative(自主性の尊重)
- 8 「リーダー・グループ」の導入
- 9 アイルランド戦で「リーダー・グループ」が機能する
- 10 「ONE TEAM」は選手たちと一緒に考え出した。
- 11 Diversity&Inculusion(多様性の受容)
- 12 日本のスポーツ界は外国人選手と共に強くなってきた。
- 13 日本は多様性を受け入れることで進化してきた。
- 14 合言葉は「グローカル」
- 15 【まとめ】サーバント・リーダーシップ&シェアード・リーダーシップ
- 16 「シェアード・リーダーシップ」とは。
- 17 人間としての成長。
2015年イギリスにて第8回ラグビー・ワールド・カップ(W杯)が開催されました。日本はそれ以前、W杯では1勝しかしていない「世界で勝てないチーム」でした。このチームを変えたのが、オーストラリア出身のエディー・ジョーンズHC(ヘッド・コーチ)です。
エディHCは、「世界一の練習量」と言われた厳しいトレーニング(ハードワーク)を選手に課しました。「ハードワーク」は2015年頃、ビジネス雑誌にも乗る流行語になりました。その成果も出て、日本代表は世界の強豪「南アフリカ」を撃破する奇跡を起こしました。「スポーツ史上最大の番狂わせ」と報じるメディアもあり、その偉業は「ブライトンの奇跡」と呼ばれます。
日本に輝かしい功績をもたらしたエディーHCの後任は誰になるのか。多くのメディアが注目するなか、2016年就任したのがジェイミー・ジョセフ(Jamie Joseph)HCです。

Jamie Joseph
ジェイミー・ジョセフは、ニュージランド出身の元ラグビー選手です。ニュージランド代表チーム「オールブラックス」にも選出され、1995年南アフリカで開催された第3回W杯で、準優勝メンバーのひとりになっています。
第3回W杯といえばアパルトヘイト(人種差別)問題を解決に導いたネルソンマンデラ大統領が観戦した試合です。この時、「オールブラックス」と「南アフリカ」が決勝で戦い、「南アフリカ」が優勝しています。その歴史的背景と優勝までの軌跡は映画『インビクタス 負けざる者たち』(主演:マット・デイモン)になっています。

(ワーナー・ホーム・ビデオ)
ちなみに、第3回W杯の時、日本代表は「オールブラックス」と対戦していて、「145対17」という屈辱的大敗を喫しています。日本が「ブルームフォンテンの悲劇」と呼ぶこの試合にジェイミー・ジョセフは出場していました。
その後、来日し西日本社会人リーグの「サニックス」(現・宗像サニックスブルース)に所属し、2000年までプレーをしています。1999年には、平尾誠二監督のもと、日本代表の選手としてウェールズで開催された第4回W杯に出場。ジェイミーHCは、日本と深い縁のある人物です。
2002年に現役を引退後、ニュージランドに帰国し様々なキャリアを積むと、2011年、「スーパーラグビー」(SR)の「ハイランダーズ」のHC(ヘッドーコーチ)に就任します。

「スーパーラグビー」(SR)とは、「日本」「ニュージーランド」「オーストラリア」「南アフリカ共和国」「アルゼンチン」の計5カ国のプロチームが参加する世界的なラグビー・リーグです。日本のチームは「サンウルブズ」ですね。
ラグビー王国ニュージーランドには「クルセーダーズ」「ハリケーンズ」など計5つのチームがあります。「ハイランダーズ」はそのひとつです。就任当初、無名の選手が多く弱小チームだった「ハイランダーズ」をジョセフHCは、わずか4シーズンで優勝へ導いたのです。

著作権者 江戸村のとくぞう
優勝までのプロセスで痛い目にもあいました。チームが実績をあげ始めるとオールブラックスに選ばれる有名選手が加入してきました。しかし、2013年、チームは低迷することになります。
スター選手たちは「チームへの忠誠心」に乏しく、ジェイミーHCは、例えスター選手であっても、マイナスの影響を及ぼす選手たちには、辞めてもらう決断をします。そして、2015年、スーパーラグビーで頂点に立ったのです。
「ハイランダーズ」時代に学んだ指導者としてのリーダーシップが、日本代表での「チームづくり」に活かされていきます。
それでは、ジェイミーHCのリーダーシップを3つのキーワードで整理し、話しを進めていきます。3つのキーワードは次の通りです。
- Change(変えるべきは変える)
エディー・ジョーンズ前監督とは異なる戦略を選択した - Self-initiative(自主性の尊重)
自ら考え、自ら決断でき、自ら実行できる選手を育てた - diversity&inclusion(多様性の受容)
海外選手の起用によってチームに多様性を育んだ

クリックするとAmazonへ!
前エディー・ジョーンズHCは、「世界で勝てない」と言われていたチームを世界レベルに引き上げました。「南アフリカ」に勝利する奇跡まで起こし、その実績を考えると「エディー流」を踏襲していくのは正攻法です。
「エディー流」のチームづくりは、徹底した「マネジメント」(管理)が、その特徴でした。練習や試合での詳細な指示はもちろんのこと、ホテルでの服装までエディー前HCは厳しく注意し管理しようとしました。
「笑わない男」というネーミングで一躍有名になった稲垣啓太選手は、「エディー流」をこう振り返っています。

著作権者 江戸村のとくぞう
プロップ 稲垣啓太
『日本経済新聞』(2019/9/27)
「エディーは自分で何でもマネジメントしたがった。準備したことをやれ、これをやれば大丈夫という理念のもとでやっていた」
エディー流の「管理」に対して、ジェイミーHCは選手の「自主性・主体性」を重視し、それをチームの風土にしようとしました。W杯開催の約2年前、2017年にジョセフHCはスポーツ雑誌『Number』のインタビューで、こう答えています。

クリックするとAmazonへ!

ヘッドコーチの重要な仕事とは、選手が信じることのできる環境を創造することです。選手に自信を与えなくてはならない。それが私の務めです。
『Number』 929号(文藝春秋)p19
この発言をリーダーシップ理論に当てはめれば、ジョセフHCのリーダーシップ・スタイルは、「サーバント・リーダーシップ」と言えます。
エディー監督は、厳しい練習(ハードワーク)とプライベートにまで踏み込むマネジメント(管理)で、強いチームをつくりました。これに対して、ジョセフHCは、厳しい練習(ハードワーク)は踏襲しつつも、チーム全体の風土は「自主性・主体性」を尊重し、「選手が信じることのできる環境を創造すること」に力を注いだのです。

自分がリーダーとして直接、指示命令をして組織をマネジメント(管理)するのではなく、メンバーの自主性・主体性を信じて、リーダーは一歩引いて「環境づくり」に力を入れる点は、「サーバント・リーダーシップ」の特徴です。
ハードワークに関しては、「エディー時代より厳しい」と漏らす選手もいました。引き継ぐべき部分は引き継ぎ、ですが、変えるべきは変えて、ジョセフHCは自身の「リーダー哲学」を貫き通したのです。
「チェンンジ・リーダーシップ」という言葉もある通り、リーダーシップとは「創造的破壊」を引き起こし「変革」を行うことがその役割のひとつです。「マネジメントとリーダーシップの違い」を明確に区別する議論があります。マネジメントの機能が「秩序の維持」であれば、リーダーシップのそれは「創造的破壊」です。
創造的破壊が組織(チーム)で起きる時、必ず、抵抗するものが現れます。「うまくいったやり方があれば、それを続けたほうがよい」と考えるのが人間です。リーチ主将も抵抗したひとりでした。彼はジョセフHCとの関係について、『ラグビーマガジン』(2019年11 月号)のインタビューで、こう答えています。

Author 江戸村のとくぞう
リーチ・マイケル 主将
『ラグビーマガジン 2019年11 月号』(ベースボール・マガジン社)p10
「キャプテンになってから、正直、二人の間でごちゃごちゃありました。エディージャパンのスタンダードと、ジェイミーのそれとは違って、たとえばホテル内の服や靴についてもすごく厳しかった。ジェイミーはそうじゃなくて、〝もうちょっとゆったりして練習できる環境を作りたい〟と。
僕は最初(エディー)同じくらい厳しくやりたかったけど、柔軟性を持って、コミュニケーションをとりながらやってきた。
(中略)
リーダーミーティングで言い合いもあるし、そこで初めていい関係が作れる。お互い曲げられないところもあって、どのタイミングか分からないけど、二人で同じページを見られるようになりました」

(ベースボール・マガジン社)
クリックするとAmazonへ!
これはツイッターで話題になったゲームですが、「〝もうちょっとゆったりして練習できる環境を作りたい〟」というジョセフHCの想いが本物であったことがわかります。エディーHCの時には、なかった雰囲気ですね。
ラグビーの戦い方も、ジョセフHCは、「エディー流」から変えていきました。
「エディー流」は、できるだけキックを使わず、パスを主体にして「ボールを保持」(ポゼッション)し続ける戦い方です。ラグビーでは、チームがどれだけ「ボールを保持」できるかを「ボール支配率」という指標にしています。「ボール支配率」は、「どちらのチームが試合を有利に進めているか」を判断する重要な指標です。ただ、2015年、南アフリカを撃破した時は、キックも使い、戦い方を変えることで、南アフリカの選手たちを混乱させることに成功しました。
ジョセフHCは、2016年、就任当初からキックを多用する戦略を選択しました。ラグビーでキックを蹴ると、敵チームのボールとなる可能性が高くなり、「攻撃を受ける」というデメリットがあります。ジョセフ監督は、この点について、2018年「NHK」のインタビューでこう答えています。

体格で勝る、パワフルなチームに我々が勝つには、相手を混乱させる必要があります。スクラムからラインアウト、モールからスクラムといったスローな展開の場合、経験豊富でパワーのあるチームには苦戦を強いられてしまいます。それで有効なのがキックです。
出典:『NHK SPORT STORY』〜ラグビーW杯まで1年 日本代表ジョセフヘッドコーチ インタビュー (2018年9月26日)
キックを蹴ることでグランドに生まれる混乱状態を「アンストラクチャー」(unstructured)と言います。スクラムやラインアウトのセットプレーは、敵味方の陣形が整っている「ストラクチャー」(組織化・構造化された)状態です。これに対して、ボールが動いている時に、キックを蹴ると、敵味方の陣形が乱れますので、組織立っていない「アンストラクチャー」状態となります。
「エディー流」がキックをあまり使わず「ストラクチャー」を継続する戦い方であれば、「ジェイミー流」は、キックを主体に「アンストラクチャー」からチャンスを作り出す戦法でした。

ここにも2人のカラーが表れていますね。ボールを味方チームで保持する「ストラクチャー」(エディー流)は、プレーを自分の意図した通りに管理する「マネジメント型」と言えます。
ボールを蹴って、「アンストラクチャー」(ジェイミー流)からチャンスを作り出すプレーは、「創造的破壊」を意図したプレーであり、これは「リーダーシップ型」と言えます。
戦い方を「アンストラクチャー」主体にすると、求められるのは、選手たち個々の自主的な判断力です。それもあってジョセフHCは、「自主性の尊重」を重視したのです。
2017年『Number』のインタビューで、「日本人の強み」について尋ねられたジョセフHCは、こう答えています。

クリックするとAmazonへ!

素早さ、スキルフルであること。全般は、NZで用いる言葉なら、コーチャブルであるところ。コーチをしやすいのです。協力的で忍耐強い。これはラグビーに限らず、広く日本の文化なのだと思います。コーチの立場としては、そこに加えて、もっと選手の側から率先して動きを考えることを求めたい。みずからをプロデュース、みずからをオーガナイズできれば、さらにチームは強くなります。
『Number』 929号(文藝春秋)p22
「アンストラクチャー」から勝機をつかむゲーム戦略・戦術を遂行していくためには、自分で考え、自分で判断し、自分から率先して動く自律的マインド・セットが求められます。この「自主性・主体性」を育むために、つまり、「リーダーシップ開発」を目的としてジョセフHCは、選手たち自身で考えてもらう「リーダー・グループ」という仕組みを導入しました。
スポーツチームで一般的なのは、キャプテン(主将)と副キャプテン(副主将)がリーダーとなり、チームをまとめていくスタイルです。
2016年、「ジェイミー・ジャパン」で最初の日本代表チームが結成された時、「ダブル・キャプテン制」が導入されました。堀江翔太と立川理道の2人がキャプテンに選ばれたのです。当時、ジェイミーHCは、こう言っていました。

「このチームにはキャプテンが2名いますが、この共同キャプテン制というのは自分とトニー・ブラウンとが過去に成功してきたやり方を踏襲したものです。選手たちと同じ方向に進みながら、短期間でチームをひとつにしていくには効果的な方法だと思っています。(中略)
我々の仕事のひとつは、日本のラグビーを引っ張っていくリーダーを育てていくこと。」
出典:「日本ラグビーフットボール協会」HP「日本代表 メンバー発表記者会見レポート」2016.10.28 (金)
この発言からわかるのは、就任当初から、コーチ陣に頼ることなく、選手たち自身で「ONE TEAM」になれるリーダーを育成しようとしていた点です。
そして生まれたのが「リーダー・グループ」です。キャプテンと副キャプテンでチームを引っ張るのではなく、各ポジションからリーダーを選び、個々の選手がリーダーシップを発揮し、ひとつのグループになって「ONE TEAM」を目指します。あるミーティングでは、選手自らが話す内容を考え、司会や運営もしました。

「リーダー・グループ」での経験を積めば、試合の時に、誰もがキャプテンを務められる「チームづくり」を実践してきたと言えます。試合中、意思決定はキャプテンに任せて「自分は関係ない」という意識でいるより、チーム・メンバー全員が「自分もキャプテン」という強い意識を持てば、「ONE TEAM」になることができますね。
2019年W杯の時には、選手10人で「リーダー・グループ」が構成されていました。
※2019年W杯時点
この「リーダー・グループ」が有効であったことを証明したのが2019年W杯第2戦の対アイルランドです。主将リーチ・マイケルは第1戦(対ロシア)でのプレーが不調だったため控え選手に回りました。代わりにゲーム・キャプテンを務めたのが南アフリカ出身のピーター・ラブスカフニ選手です。

Author 江戸村のとくぞう
少しぐらい調子が悪くても、キャプテン(主将)は「精神的支柱」としての役割があるので、先発させるのがセオリーです。ですがジョセフHCは、リーチ主将を外しました。「リーダー・グループ」での経験を積み、主将なしでも戦える「ONE TEAM」になっていたことに確信があったからです。

ただ、リーチ選手を先発から外すことで、彼を奮起させる「裏の意図」もありました。ジョセフHCの狙いは的中します。前半30分、アマナキ・レレイ・マフィの負傷交代でリーチ選手がグランドに入ると、リーチ選手は本来の調子を取り戻し、チームの流れを一気に変えました。
W杯の開催直前、「ONE TEAM」での取り組みを総括するリーチ主将の言葉が掲載されています。
リーチ・マイケル 主将
『日本経済新聞』(2019/9/7)
「前回大会はW杯の1~2週間前になって自主性が生まれたけど、それまでは(当時のHCの)エディー・ジョーンズが言うことをひたすらやった。今は細かいチームづくりは選手がやる」
選手たちが自らリーダーシップを発揮し「細かいチームづくり」をやったからこそ、「ONE TEAM」となって、世界第2位のアイルランドに勝利する奇跡を起こすことができたのです。
2019年ラグビーW杯が盛り上がりを見せ、「ONE TEAM」は、多くのメディアがニュースで取り上げ、巷でも口にされるようになりました。この言葉は、2016年、記者会見の場で発表されたものです。ジェイミーHCは、こう発言していました。

「9月1日に来日して以来、全員がひとつになって目標に向かっていくためのスローガンを考えてきました。それも、自分ひとりで考えるのではなく、選手たちと一緒になって考えていくべきだと感じて、1回目のミニキャンプの際にリーダー陣と相談を始めました。
どんなチームにしていきたいのか、どんなラグビーをしたいのか、ファンのみなさんからどういう存在だと思われたいのか。
そんなテーマで選手たちに自分たちで考えてもらい、決めたスローガンが『ONE TEAM FOR JAPAN, ALL ATTITUDE』です」
出典:「日本ラグビーフットボール協会」HP「日本代表 メンバー発表記者会見レポート」2016.10.28 (金)
『ONE TEAM FOR JAPAN, ALL ATTITUDE』。このスローガンは、コーチ陣が決めて、選手たちに知らされたものではなく、「選手たちに自分たちで考えてもらい」決められたものだったのですね。
企業組織で言えば、経営陣が決めて「トップダウン」したものではなく、ミドル・リーダー(中間管理職)など社員と一緒になって「参画型」で、考え出されたものだと言えます。就任当初からジョセフHCが、いかに選手の「自主性・主体性」を重視していたのかがわかるエピソードです。
2019年W杯で、試合の切り札として何度も登場した田中史明選手も、こう発言しています。
スクラムハーフ田中史明
『日本経済新聞』(2019/9/30)
「今の代表は昔と全然違う。コーチに頼るだけでなく、自分たちでチームを作る、自分たちで進化したチームだと思う。今までの代表よりもさらに誇れるチームになった」
リーチ・マイケル 主将は、W杯開催前、『Number』 986号(文藝春秋)に、こんな言葉を残しています。

クリックするとAmazonへ!
リーチ・マイケル 主将
『Number』 986号(文藝春秋)p22
「理想はコーチのいないチーム。コーチに何も言われなくても自分たちで決められるチームです。試合ではHCの指示をいちいち待っていられない。自分たちで考えて解決しないといけない。それはジェイミーも言っていることです。ジェイミーはこのチームを伸ばすためにどうしたらいいか、すごく考えてサポートしてくれている」
「選手の自主性を尊重する」。ジョセフHCの「リーダー哲学」が、徹底され最後まで一貫していたからこそ、選手たちのリーダーシップは見事に開花したのです。
日本代表ラグビー・チームへの「定番の批判」があります。それは、「外国人選手が多くて、あれでは日本代表じゃない」という批判です。
2019年W杯では31人の登録選手中、15人が外国出身者でした。ラグビーは日本国籍を持っていないくても「3年間継続して日本に住む」など、一定の基準をクリアすれば代表選手になれます。その国の国籍を持たずとも代表選手になれるルールは世界標準であり、他国のチームも外国人選手を多く起用しています。
ビジネスの世界では、グローバル化が一気に進展した1990年代、「ダイバーシティ」(人材多様性)という言葉が企業組織を語る上での重要なキーワードになりました。「多様な人材が組織の強さを生み出す」。そんな考え方がセオリーとなり、職場で外国人の姿を見かけることも日常的な風景となりました。

日本のスポーツ界は、レベルの高い外国人選手を受け入れることで強化されてきた歴史があります。1992年に発足されたサッカーの「Jリーグ」は、その最たるものです。世界で活躍するトップレベルの選手がチームに加入し、実力の底上げを図ってきました。バスケットの「Bリーグ」も同じです。
日本ラグビー界も、ニュージランドや南アフリカでの代表経験がある「すごい選手」たちが社会人リーグに次から次へと参戦し、着実にプレーの質を高めてきました。「ダイバーシティ」(人材多様性)をチームにもたらすことで、日本人は世界で通用するようになっていったのです。
2010年代以降、ビジネス界では、「ダイバーシティ&インクルージョン」と言われるケースが目につきます。
インクルージョン(inclusion)とは、「包摂」「包含」を意味します。ダイバーシティ(多様性)は、グローバル化が進む中で、日本人だけで組織をつくる閉鎖的な「島国根性」から脱却しようと「組織に多様性をもたらすこと」(多様性の進展)を目的としていました。
一方で、社会的マイノリティ(障害者やLGBT)を、社会に受け入れようとする価値観が広がり始めると、多様性を組織に包み込みこもうとする「インクルージョン」(多様性の受容)の考え方が生まれてきました。そこで、「ダイバーシティ&インクルージョン」と言われるようになってきたのです。
仏教しかり、自動車しかり、日本は古くから海外からの多様な文物を取り入れ独自に進化させてきたました。その進化させたものが「日本オリジナルの文化」として世界から評価されるようになるのです。日本人は多様性を「受け入れて、融合し、進化させる」のを得意技としている民族です。これこそ日本人の「強み」です。
- 受容(インクルージョン:inclusion)
海外から多様な「よいもの」を貪欲に受け入れる。 - 融合(フュージョン:fusion)
受け入れたものを日本文化と融合させる。 - 進化(エボルーション:evolution)
融合したものを日本独自のものとして進化させる。
外国人選手の多いラグビー日本代表チームの姿は、むしろ「日本流のやり方」でつくれた「日本らしいチーム」であると言えます。ジョセフHCは、「あんなの日本代表じゃない」という厳しい批判にめげず、外国人選手を多く起用することでチームに「多様性」をもたらしました。そのことでチームがバラバラになるのではなく、逆に、日本人の強みが発揮されて「ONE TEAM」になっていったのです。
2019年7月、宮崎合宿ではチームの「ダイバーシティ」(多様性)を重視するため、「グローカル」が合言葉になっていました。「グローカル」とは「グローバル」と「ローカル」を組み合わせた造語です。
日本という地域(ローカル)と世界の選手(グローバル)の力を融合させるコンセプト・ワードが「グローカル」です。

日本の国歌にはどんな意味が込められているのか。リーチ・マイケル主将が主導して勉強会が開かれました。国歌の歌詞に出てくる「さざれ石」を見学にも行きました。合宿所には「カツモト」と命名された「赤い甲冑」が置かれました。「カツモト」とは、映画「ラストサムライ」で渡辺謙が演じた勝元盛次が由来です。
こうした「グローカル」をコンセプトにした「ONE TEAM」への取り組みは、外国人選手に日本文化を理解してもらう一助になると同時に、日本人選手も、より深く「日本」という「国」を意識し理解するポジティブな効果を発揮しています。
日本は島国で、世界有数の平和な国であるため、日本人は「国」という意識を持ちにくい国民性を持っています。

Author:長曽我部政幸
外国人選手がいなければ、「グローカル」という言葉も、国歌の勉強会も「さざれ石」の見学会もなかったでしょう。外国人選手がいるからこそ、「日本のよさ・強み」を考え、日本人選手もまた「日本人らしさ」を自覚でき、そのマインドセットが「ONE TEAM」をつくりあげる原動力になったのです。

(ベースボール・マガジン社)
クリックするとAmazonへ!

「今の日本代表はワンチームになった。ヘッドコーチとして、そこを一番に重んじて、コーチ、チームを主導してきた。チームのためなら何でもできる、体も張れる、死ぬ覚悟でいけるという気持ちを持った選手たちを輩出するのが、自分の一つの目標でもある。いま選手たちが非常に意思統一を図れていて、同じを絵を見て励んでいる。」
出典:『ラグビーマガジン 2019年11 月号』(ベースボール・マガジン社)p85
就任当時からのジョセフHCの発言を追いかけると、チームを強くする「環境づくり」に力を入れていた点が浮き彫りになります。自分がカリスマ的な存在となり、先頭に立ってチームを引っ張るのではなく、選手たちの自主性を尊重し、選手たちで考えさせ、選手たちがヒーロになるように「サポート」していくスタイルが「ジョセフ流」のリーダーシップです。
リーチ・マイケル主将は「ジェイミーはこのチームを伸ばすためにどうしたらいいか、すごく考えてサポートしてくれている」と言っていました。
このスタイルは、まさに「サーバント・リーダーシップ」の典型と言え、日本ラグビー史上初のW杯ベスト8に導いたジョセフHCは、「サーバント型リーダー」だったと言えます。
また、「リーダー・グループ」を結成し、「誰もがリーダーとなってリーダーシップを発揮していく」というコンセプトは、リーダーシップ理論では「シェアード・リーダーシップ」(Shared Leadership)という考え方に当てはまります。
「シェアード・リーダーシップ」について、コーチングの大家マーシャル・ゴールドスミスは、『Harvard Business Review』掲載の論文で、こう述べています。
シェアード・リーダーシップとは何か。その目的は、組織内のすべての人材の能力を最大限に引き出すことだ。そのために各人に権限を与え、それぞれの専門分野でリーダーとしての役割を担う機会を提供する。
『Harvard Business Review』(Web版 ダイヤモンド社)
『リーダーシップの共有が組織と人を強くする』
ゴールドスミス氏が書いたことは、日本代表チームが実践した「リーダー・グループ」の仕組みにマッチします。「理論倒れ」という言葉がある通り、理論は「机上の空論」に終わることもあります。ですが、ジョセフHCの実践とその成果は、「シェアード・リーダーシップ」の有効性を証明した事例としても、とても貴重なものです。
本稿を書くにあたって、様々な資料を読み込みました。その中で、ジョセフHCの根底にある「リーダー哲学」ではないかと、強く感じた言葉があります。『文春オンライン』に掲載されていた、次のものです。

「チームカルチャーというのも私のコーチング理念の大きな部分を占めます。
ラグビー選手としてだけではなく、人間として成長して欲しい。
これまでも私はここに熱意を持ってやってきました。 1人よがりではなく、チームが進む方向に自分を合わせて、 真剣に取り組むところと楽しむ部分の バランスが優れている選手を求めています」
出典:『文春オンライン』「ラグビー日本代表「“名将”ジェイミー・ジョセフってどんな人?」 指揮官を知る“3つのキーワード”」(ラグビージャーナリスト村上 晃一)
冒頭に書いた通り、ジョセフHCは指導者としてスーパーラグビー「ハイランダーズ」を優勝に導いた経験があります。輝かしい功績です。ただ、忠誠心の乏しいスター選手を加入させてしまい、2013年、チームが低迷するという辛く苦しい経験もしています。
この経験もあって「ラグビー選手としてだけではなく、人間として成長して欲しい。」という思いをより強く持ったのでしょう。
「人間としての成長を願う。」
この「リーダー哲学」は、目新しさは無いかもしれませんが、やはり、どんな時代でもチームをつくりあげるリーダーが持っていたい信念です。
人間的成長があってこそプレーも成長する
このことは歴史上の多くの名監督、名コーチ、名リーダーたちが口にしていることですね。試合には勝たなければいけませんが、試合に勝てばいいのではありません。
大人の知性・意識の発達を研究する「成人発達理論」が注目されています。かつて心理学では成人したら心は成長しないと考えられていました。ですが、「成人発達理論」の知見が蓄積され、人間は生涯を通して成長していくことが常識になりつつあります。
ジョセフHCが大切にした「人間としての成長」は、経営学・組織行動学、ひいては「人材育成」「人材開発」という枠組の中でもキーになる重要なコンセプトになっています。
「サーバント・リーダーシップ」と「シャアード・リーダーシップ」を融合させることで「ONE TEAM」は生まれました。そのコアに「人間としての成長」を願っていたジョセフHCの「リーダー哲学」を見逃すことはできません。
選手たちの「人間としての成長」があるからこそ、チームは「ONE TEAM」になれるのです。
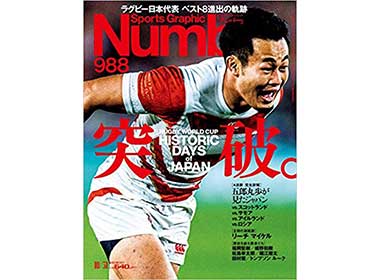
クリックするとAmazonへ!
9月28日(土) 日本代表 19-12 アイルランド代表
10月5日(土) 日本代表 38-19 サモア代表
10月13日(日) 日本代表 28-21 スコットランド代表
10月20日(日) 日本代表 3-26 南アフリカ代表
(文:松山 淳)